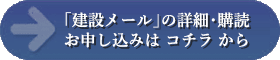|
【担い手確保育成】技術者の流動化図る/業界で人材バンク構築を
国土交通省は、技術者の人材育成や流動化について将来的な方向性を示した。技術者版CCUSとも言えるデータベースを整備して人材バンクを構築し、建設業界全体で技術者の流動化を図ることや、AI活用による技術継承などが掲げられている。
続きを読む
技術者の育成・流動化などに関する方向性は、13日に開かれた有識者会議のとりまとめとして提示されたもの。今後は次期技術基本計画に反映され、建設行政を進めるうえでの指針となる。
とりまとめにおける技術者確保・育成の方向性に関する主な内容は次の通り。
◇人的資本投資の強化
従来は人材を「資源」と位置づけ、必要な予算を「コスト」とみていた。これから企業が成長するには、人材を「資本」としてとらえて投資を行うことで社員の気概(やる気)を創出することが重要。技術者本意の人事制度を積極的に導入すべきであり、国は企業の取り組みを積極的に支援すべき。
◇技術者データベース整備
官民含めて建設業界全体で職種や組織にとらわれない技術者データベースを整備する。それぞれの資格や経歴、実績などを一元的なシステムで集約し、建設部門の人材バンクを構築。業界全体で活用することで、人材の流動化を図る。業界内において、人材の流動を歓迎する意識、転職で実績ある人材を重宝する意識への改革が必要。
◇学生への発信
土木を学んだ学生が、建設業界における情報不足を理由に業界離れが起きないよう、産学官が連携し、DXも活用して、業界の魅力をわかりやすく伝える取り組みを行う。
◇自学によるDX内製化
現場の課題解決のために社員が自学でDXを内製化する風土を醸成すべき。また役職者や中堅によるデジタル技術の理解を目的としたITスキル向上も図るべき。
◇建設ディレクター育成
ICTを活用して工事関係書類をバックオフィスで行う建設ディレクターを育成し、現場技術者の負担を軽減して品質管理に専念できるようにする。女性や事務系社員の活躍の機会が広がることも期待。
◇AI活用による技術継承
メンテナンスに関わる品質管理や構造物診断などの技術的知見・判断の技術継承に向け、先人が蓄積したアナログデータとAIを結びつけ、技術的判断を支援するシステムを構築。技術者を本来の創造的業務に従事できるようにする。若手育成の円滑化や外国人材育成への活用も期待。
ちょこっと補足
とりまとめを行った有識者会議の小澤一雅座長は、どうやって人材の流動性を高めるべきか、それによって企業が成り立つのか、こうした部分が今後の課題になると見ている。また、技術者は流動化をポジティブにとらえると思われるが、企業側がプラスの視点で見られるか。これについて建設産業の全体で議論していく必要性を示している。
◇関連記事(有料購読者限定機能)
✎ 【社会資本整備】重点計画の見直しを/施策の方向性を議論〈2025/02/13〉 ✎ 【関東地整】各建協、都県が一堂に/担い手確保で17日初開催〈2025/02/12〉 ✎ 【JS】下水道技術検定第1種/合格者を発表〈2025/02/10〉 ✎ 【日本CM協会】売上高合計は407億円/24年度CM業務市場調査〈2025/02/10〉 ✎ 【海外インフラ】優秀技術者24年度は14人/13日に表彰式を開催〈2025/02/07〉
〈2025/02/14配信〉
この記事は「建設メール」のサンプルです。 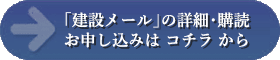
日本工業経済新聞社 本社 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-11
|