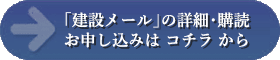|
【道路陥没】対策検討委が初会合/メンテナンスのあり方議論
 | 陥没事故を踏まえた対策委員会が初会合 |
埼玉県八潮市で発生した下水道に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえ、国土交通省は対策検討委員会(委員長・家田仁政策研究大学院大学特別教授)を設置し、21日に初会合を開いた。会議では事故概要や下水道施設管理の現状を確認。今後の下水道管における点検調査やインフラメンテナンスについて議論した。委員会は3月3日に現地調査を予定。春に中間とりまとめ、夏には最終とりまとめを作成する。
続きを読む
会議の冒頭、中野洋昌国交相は「管路メンテナンスを再建し、このような事故を二度と起こしてはならないという強い決意で対策を講じたい。事故再発を未然に防ぐため、重点的に点検を行う対象や頻度、技術など点検のあり方、道路管理者をはじめとする他の管理者とのリスク情報の共有などについて、春ごろまでにとりまとめていただきたい。また今後の施設維持更新や再構築、制度のあり方についても議論していただきたい。本委員会の議論は今後のインフラ全体のメンテナンスにもつながっていくと考えている」とあいさつした。
家田委員長は「こういう事態が再び起こることのないよう緊急に施策を考え、中長期的なマネジメントのあり方も検討したい。道路であれば交通を迂回して通行止めにして迅速に復旧できる。しかし下水道は流れてくる水を簡単に止めることができない。迂回路もないところが大きな特徴。今回の事態は何重もの意味で真剣にとらえなければいけない。インフラマネジメントは万全というところから程遠い。これからじっくり考えていかなければいけない」と述べた。
会議では、八潮市の事故状況やこれまでの対応を確認。現在は陥没箇所の水位低下に向けてバキューム車や排水ポンプ車で輸送・放流していることを共有した。
下水道施設管理の現状については、今回の事故現場と同様の大規模管路において実施した緊急点検の結果を確認。さらに現在の点検・調査の手順や技術、下水道管路腐食と道路陥没のメカニズム、下水道を供用しながら施工する更生工法の種類などの説明が行われた。
議論では、今回の事故原因は不明ではあるものの「構造・地盤・硫化水素・地下水などが複合的に要因となっているのではないか」との考え方もあり、「一刻も早く点検すべきところを迅速に実施すべき」という方向性が出された。
事故後に全国で行われた緊急点検では埼玉県内で3カ所異状が見つかったが、他地区では異状が発見されなかった。家田委員長は「それで安心するのではなく、さらに方法も場所も選んで質の高い調査をすべき」と考えを示した。
またインフラメンテナンスの中長期的な対応については「地下空間は未知の要素が大きい。地下の状態を把握して包括的に参照できるようにすべき」として、『地下空間統括デジタルシステム』が必要との意見も出た。同システムがあれば、トラブルがあった時にも新しい事業を行う際にも活用できると見ている。
対策検討委員会は日本下水道協会理事長、埼玉県下水道事業管理者、東京都下水道局長、国土技術政策総合研究所上下水道研究部長、日本下水道管路管理業協会会長、土木研究所地質・地盤研究グループ長、大学教授6人の計12人で構成している。
◇関連記事(有料購読者限定機能)
✎ 【流域治水】実務者会議を開催/府省庁が取り組み報告〈2025/02/21〉 ✎ 【地理空間情報】人流データ活用イベント/26日オンラインで開催〈2025/02/21〉 ✎ 【群マネ】効果や運用方法を議論/25年度に手引き作成を〈2025/02/19〉 ✎ 【官民連携】先導的取り組みを支援/3月4日まで提案募集〈2025/02/19〉 ✎ 【インタビュー】寺田吉道 国土交通審議官/中小企業の海外進出を支援〈2025/02/19〉
〈2025/02/25配信〉
この記事は「建設メール」のサンプルです。 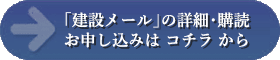
日本工業経済新聞社 本社 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-11
|